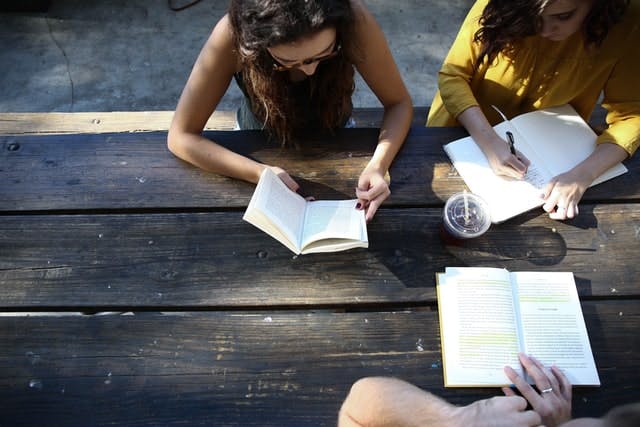医師の方は高い収入を得られる一方で、累進課税により重い税負担を抱えているのが現実です。
「もっと効果的な節税方法はないだろうか」
「将来の資産形成を進めたい」
とお考えの方も多いのではないでしょうか。
そんな医師の方におすすめしたいのが不動産投資です。節税効果だけでなく、インフレ対策としての資産保全や安定した賃料収入による資産形成が実現でき、医師という職業の高い信用力により有利な融資条件も期待できます。
またINVASEに会員登録されている医師の51%の方は不動産投資を経験されています。
そして最も多い投資の目的は節税、と回答頂くなど、節税面でメリットを感じられている方も多いようです。

※2025年7月時点のINVASE会員データ
本記事では、医師に不動産投資がおすすめな理由から具体的な節税効果、物件種別の比較、注意すべきリスクまで包括的に解説いたします。
※時間がない方へ・・・今すぐ節税額のシミュレーションを知りたい方は「タワマン投資サービス」、不動産投資ローンの借り入れ可能額を知りたい方は「バウチャーサービス」をご利用ください。いずれも無料でお申し込み頂けます。
INVASE事業責任者・渕ノ上(ふちのうえ)

コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社 取締役CSO
立教大学法学部法学科卒業。在学中より法律系予備校に通い法律を学ぶ。大学卒業後コンサルタントとしてECサイト運営会社を起業すると同時に不動産コンサルタントとしても業務を開始、不動産関連法律資格の講師として活動。
【保有資格】
不動産コンサルティングマスター / 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 管理業務主任者 / AFP / 2級ファイナンシャルプランニング技能士 / マンション維持修繕技術者 / マンション建替士
>不動産ナビゲーター・渕ノ上 弘和のプロフィールはこちらから
>不動産投資の基本から応用までを解説。Youtube「不動産ナビゲーターチャンネル」はこちらから
医師に不動産投資がおすすめな理由は?
高収入だからこそ、節税効果が見込める

医師の皆様が不動産投資を選ぶ大きな理由の一つが、高い所得税率に対する節税効果です。
不動産投資では、減価償却費、物件購入時の諸費用、一部交際費などを経費として計上できるため、給与所得と損益通算することで所得税・住民税の課税所得を圧縮できます。
特に累進課税制度により高い税率が適用される医師にとって、不動産所得の赤字を給与所得から差し引くことで得られる節税効果は大きくなるでしょう。
さらに、相続税対策としても不動産は現金よりも評価額が下がるため、将来的な資産承継においても税制上のメリットを享受できます。
このように不動産投資は、高所得者である医師の税負担を軽減する有効な手段として機能していると言えるでしょう。
※参考>>国税庁 所得税
融資も受けやすく、レバレッジが効くため、幅広い選択肢を持てる
医師は金融機関から高い信用力を評価され、不動産投資における融資審査で有利な条件を得ることができます。
安定した高収入と社会的地位により、一般的な会社員と比較して低金利での融資や、より高い融資比率での借入が可能となるケースが多く見られます。
このレバレッジ効果により、自己資金が限られていても、より高額な物件への投資が実現でき、投資選択肢の幅が広がります。
例えば投資用として一般的なワンルーム物件、一棟アパートだけでなく、1LDK以上のファミリータイプの物件、タワーマンションの物件等、幅広い選択肢の中から、最適な選択が可能です。このような融資面での優位性は、医師が不動産投資で成功するための重要な要素の一つと言えるでしょう。
忙しくても管理会社に任せられる手軽さ
日々の診療や当直、学会準備などで多忙な医師の方にとって、投資に時間を割くことは難しいと思います。
しかし、不動産投資では管理会社に物件管理を委託することで、入居者募集から家賃回収、設備トラブル対応まで、煩雑な業務を任せることが可能です。
株式投資のように日々の値動きを気にする必要もなく、一度入居者が決まれば安定した賃料収入を期待できるため、本業に集中しながら資産運用を行うことできます。
このような手軽さから、時間的制約の多い医師にとって不動産投資は取り組みやすい投資手法だと言えるでしょう。
不動産投資が医師の節税になる理由とシミュレーション
減価償却費と経費計上による所得圧縮の仕組み
不動産投資における節税効果の肝は、減価償却費と各種経費の計上による所得圧縮にあります。まず減価償却費について詳しく説明しましょう。
減価償却とは、建物の購入価格を法定耐用年数で割って毎年経費として計上する仕組みです。
構造別の法定耐用年数は、木造22年、軽量鉄骨造27年、鉄筋コンクリート造47年となっています。例えば、建物価格2400万円のRC造マンションの場合、年間約51万円(2400万円÷47年)の減価償却費を計上できます。
中古物件の場合は、「(法定耐用年数-築年数)+築年数×0.2」で計算した年数、または簡便法として法定耐用年数の20%を使用します。
築20年の木造物件なら、簡便法で約4年(22年×0.2)となり、短期間で大きな減価償却費を計上できるメリットがあります。
ただし、木造物件は減価償却期間が短く節税効果は高くなりやすいものの、資産価値の下落も大きくなりやすい点に注意が必要です。
上記以外にコストセグリゲーションという手法を使う事で、より短期間で大きな減価償却を狙う事も可能です。具体的には、建物の設備部分を建物本体と分離して短期償却する手法で、初期の節税効果を大幅に高めることができるというものです。
事例も交えた詳細説明をご希望の方は無料カウンセリングサービスJourney(ジャーニー)をご利用ください。
不動産投資では減価償却費以外にも多くの経費を計上できます。代表的なものとして、管理費、修繕費、固定資産税、都市計画税、火災保険料、借入金利、税理士費用などがあります。
これらの経費と減価償却費を合計することで、帳簿上の赤字を作り出し、給与所得と損益通算して課税所得を圧縮することが可能になります。
※参考:不動産投資の減価償却について!計算や注意点
損益通算による節税シミュレーション

損益通算とは、不動産所得で赤字が出ている場合に、給与所得から差し引いて課税所得を計算する制度です。医師の方の年収別に、具体的な節税効果をシミュレーションしてみましょう。
※給与所得は概算値であり、実際の控除額は個人の状況により異なります。
※あくまでシミュレーションのため、実際の節税額は税理士までご確認ください。
このように、所得が高い医師ほど損益通算による節税効果は大きくなり、不動産投資の魅力が高まると言えるでしょう。
ワンルーム・アパート一棟・タワマン投資の特徴比較【医師向け物件選びのポイント】
ワンルームマンション投資の特徴とメリット・デメリット
ワンルームマンション投資は、医師の方々が初めて不動産投資を始める際に選択されることが多い投資手法です。
メリット
立地の良い都心部の物件であれば、資産価値の維持が期待できます。特に駅近や人気エリアの物件は需要が安定しており、長期的な価値保持が見込めるでしょう。
また、流動性が高く売却時の買い手が見つかりやすく、投資額も手頃なため比較的短期間での売却が可能です。管理面では管理会社に委託することで実務負担がほとんどなく、多忙な医師にとって取り組みやすい投資と言えます。
デメリット
物件価格が他の物件種別と比較して低いため、減価償却費や経費による節税効果は限定的です。
最大の懸念点は空室リスクで、1戸が空室になると収入がゼロになるため、立地選びが重要になります。また、家賃下落リスクや修繕費の負担も考慮する必要があるでしょう。
参考:【不動産投資】ワンルームマンション投資で失敗を避ける方法
アパート一棟投資の特徴とメリット・デメリット
アパート一棟投資は、より大きな節税効果と収益性を求める不動産投資上級者の医師の方々に適した投資手法です。
メリット
アパートは木造構造が多く耐用年数が短いため、年間の減価償却費が大きく、医師の高い所得税率に対して効果的な節税が期待できます。
また複数戸の賃料収入により収益性が高く、空室が発生しても他の部屋からの収入でリスク分散が図れます。土地と建物を一体で所有でき、建物の管理方針を自分で決められる自由度も魅力です。
デメリット
ワンルームよりも物件価格が高く、融資額も高額になるケースが多いため、金利上昇リスクや返済負担が重くなる可能性があります。
複数戸の管理が必要となり、入居者トラブルや修繕対応の頻度が高くなります。また、建物の老朽化に伴い資産価値が下落しやすく、売却時にキャピタルロスが発生する可能性があります。
一棟全体の大規模修繕費用の負担や災害リスクなども考慮する必要があり、ワンルームと比較して管理の複雑さが増すデメリットがあります。
参考:【不動産投資】一棟アパートのメリット・デメリット
タワーマンション投資の特徴とメリット・デメリット
タワーマンション投資は、資産性と節税効果の両面を重視する医師の方々に適した投資手法です。
メリット
物件価格も高額で建物価格も高いケースが多いため、長期間にわたって安定した減価償却費を計上でき、継続的な節税効果が期待できます。
コストセグリゲーション(建物の設備部分を分離して短期償却する手法)により、より短期で高い節税効果を出すことも見込めます。
また都心部の好立地に建設されることが多く、ブランド力や希少性により資産価値の維持・向上が見込めるでしょう。
また、富裕層や外国人投資家からの需要も高く、売却時の流動性が高いのも特徴です。
共用施設やセキュリティが充実しており、入居者満足度が高く空室リスクも比較的低くなります。
デメリット
初期投資額が高額で、数千万円後半から億単位の資金が必要となり、融資額も大きくなるため返済リスクが高まります。
修繕積立金や管理費が高額で、月々の維持費負担が重くなる傾向があります。
また、資産価値についても二極化が想定されており、物件見極めが非常に重要です。
参考:【有益】融資を理解すれば与信枠を超えたタワーマンションの投資が可能です!
医師が不動産投資で注意すべきリスクと対策方法
空室リスクと家賃下落リスクへの対策
不動産投資における最も身近なリスクが空室リスクと家賃下落リスクです。安定した賃料収入を確保するための対策を整理してみましょう。
空室リスクへの対策
立地選定は非常に重要で、駅徒歩10分以内、主要駅へのアクセスが良い物件を選ぶことが基本となります。
また、単身者向けなら大学や企業が多いエリア、ファミリー向けなら学校や商業施設が充実した住環境を重視しましょう。
なお、インベースでは25年7月時点で、勝どきエリアをおすすめエリアとしています。
参考:【2025年07月】不動産投資市場マンスリーレポート INVASE Flash
家賃下落リスクへの対策
築年数が経過しても競争力を保てるよう、適切なタイミングでのリフォームやリノベーションが重要です。
設備の更新、内装の現代化により家賃水準を維持できます。
また、周辺相場を定期的に調査し、相場に応じた適正な家賃設定により競争力のある物件として維持することが大切でしょう。
金利上昇リスクと返済リスクの管理方法
不動産投資では多額の借入れを行うため、金利変動や返済負担の管理が重要になります。
安定した投資を継続するためのリスク管理方法を説明します。
金利上昇リスクへの対策
変動金利での借入れが一般的ですが、金利上昇局面では返済負担が増加するリスクがあります。
対策として、借入時に金利上昇を想定したシミュレーションを行い、金利が0.5~1%上昇しても返済可能な範囲での投資規模に留めることが重要です。
また、より低金利の金融機関への借り換えや固定金利への変更、一部繰り上げ返済により元本を減らすことで金利上昇の影響を軽減できるでしょう。
※不動産投資ローンの借り換えにご興味ある方「借り換えサービス」をご参照ください。
2025年11月末融資実行分まで年率1.785%の特別金利をご案内しています。
返済リスクの管理方法
医師という職業の安定性を活かし、無理のない返済計画を立てることが基本となります。
空室や家賃下落を想定して、家賃収入がゼロでも給与所得から返済できる範囲での借入れに抑えることが安全です。
また、緊急時の資金として半年分程度の返済額を現金で確保しておくことも重要な対策と言えるでしょう。
流動性リスクと売却時の注意点

不動産は株式などと比較して売却に時間がかかる投資商品です。将来的な売却を見据えて知っておくべきポイントを説明します。
流動性リスクへの対策
不動産の売却には通常3〜6ヶ月程度の期間が必要で、市況が悪い場合はさらに長期化する可能性があります。
急な資金需要に備えて、手元資金を全て不動産投資に回すのではなく、現金や流動性の高い金融商品もバランスよく保有することが重要です。
また、売却しやすい立地の良い物件を選ぶことで、流動性リスクを軽減できるでしょう。
売却時の注意点 短期譲渡所得と長期譲渡所得
売却時には譲渡所得税が課税され、所有期間が5年を超える長期譲渡所得の税率(20.315%)を活用することで税負担を軽減できます。
また、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡益に課税されるため、購入時の契約書や改修費用の領収書などは適切に保管しておきましょう。
売却タイミングは市況や個人の資金状況を総合的に判断して決定することが大切です。
参考:国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
まとめ
医師の方にとって不動産投資は、高い所得税率を活かした効果的な節税手法であり、安定した資産形成にも寄与する投資商品と言えるでしょう。
高収入と社会的信用力により、減価償却費を活用した大きな節税効果と有利な融資条件を得られる点が大きなメリットと言えます。
物件選びでは、初期投資を抑えたいならワンルーム、高い節税効果を求めるならアパート一棟、節税・資産価値向上を狙うならタワーマンションなど、投資目標に応じた選択が重要です。
一方で、空室リスクや金利上昇リスクなどへの対策も欠かせません。立地選定や適切な借入れ範囲の設定により、多くのリスクは軽減できるでしょう。
医師という職業の強みを活かし、適切な知識とリスク管理のもとで不動産投資を行うことで、効果的な節税と資産形成を実現していただければと思います。
不動産投資をご検討の医師の方からよくある質問|Q&A
ローンは組まないといけませんか?
必ずしもローンを組む必要はなく、現金購入で不動産投資を実践されている人もいます。
しかし、多くの方が融資を活用して不動産投資を行っているのは、融資を利用することでレバレッジを効かせ、リスクとリターンのバランスをとりながら投資効率を最大化するために融資を活用しています。
購入不動産を担保にすることで低い金利でデットファイナンスを活用できるのは、不動産投資の大きなメリットです。
一方、ローンには返済リスクも伴うため、資金計画や将来の収支を十分に検討したうえで選択することが重要です。返済比率や物件の担保性にも注意しながら、慎重に検討されていくと良いでしょう。
ローンはどのくらい借りれますか?
不動産投資ローンの借入可能額は、物件の評価と申込者の信用状況に基づいて決まります。
評価方法には、収益還元法(賃料収入ベース)、積算評価(土地建物の原価ベース)、担保評価(売却可能額ベース)などがあり、金融機関によって重視する基準が異なります。
申込者の年収、自己資金、借入状況なども審査に影響します。まずはどの程度借入が出来るかを把握したい方はバウチャーサービスをご利用ください。
節税はどのくらいできますか?
節税効果は年収と物件価格によって大きく変わります。
例えば、年収1,800万円(給与所得1,605万円)の医師が減価償却費や経費により年間300万円の不動産所得赤字を生じた場合、所得税・住民税合わせて約129万円の節税効果が期待できます。
ただし、物件の減価償却費や経費の金額、個人の所得状況により実際の効果は異なるため、具体的なシミュレーションについては税理士などの専門家にご相談することをお勧めします。
現在の不動産市況ってどうですか?(2025年7月時点)
2025年1~3月のデータでは、依然として緩和的な金融環境やインフレ、税制面(住宅ローン減税)などを背景に全国的にはマンション賃料が長期的な上昇トレンドを描いています。
特に京都市以外の地域では、前期比上昇率はプラスで、なお2025年1月からの三か月平均の上昇率は、年率+9.2%となっております。
前期の年率+0.38%と比べ大きく全国的に賃料が大きく上昇していると言えます。
その中でも面積帯の広い物件の賃料上昇が全体を牽引しています。
総じて「ファミリー(60㎡以上100㎡未満) > コンパクト(30㎡以上60㎡未満) > シングル(18㎡以上30㎡未満)」の順で賃料上昇率が高くなっています。
参考:区分マンション賃料・エリアレポート_全国10地域で過去最高の賃料上昇率を記録(2025.6版)
長期的に見て資産価値が下がらない物件の条件は?
資産価値が下がりにくい物件は、駅近や生活利便性の高い立地にあることが重要です。加えて、管理状態が良く、修繕履歴が明確なもの、需要の安定した物件が選ばれる傾向にあります。
最後に
INVASEではローンの条件把握から物件のご提案、ローン付けまで一気通貫でご提案可能です。
まずは節税見込み金額を把握したい方はタワマン投資サービス、物件の購入・売却をご検討されている方や立地・条件をご相談されたい方は、無料カウンセリングサービスJourney(ジャーニー)をご利用ください。