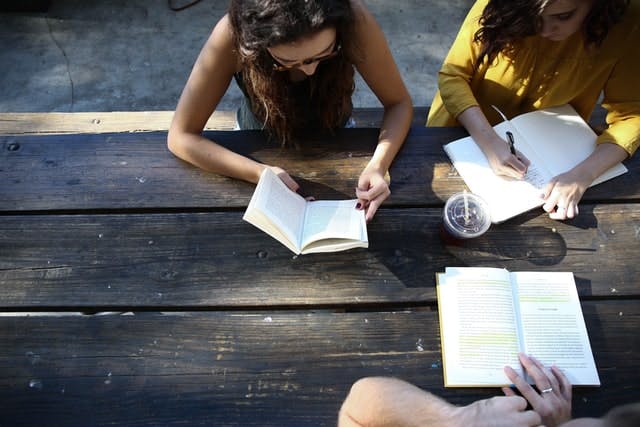昨今、銀行は大手であっても低金利が続いており、バブル前のように貯金をしておくだけでお金を増やすことは難しい状況です。
将来への備えとして貯金だけでは増えないことも考えると、資産運用の選択肢も検討したほうがよいでしょう。
資産運用というと、日々値動きが多く毎日見ておかないと行けないというような印象を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、初心者の方でも取り組みやすい資産運用の一つとして投資信託があります。
本記事では初心者が投資信託を購入する際に気をつけるべきポイントは?投資信託の選び方、注意点に関して解説していきます。
※時間がない方へ・・・今すぐ不動産投資ローンの借り入れ可能額を知りたい方は「バウチャーサービス」、不動産投資ローンの借り換え【特別金利1.575%〜】ができるのか、いくら借り換えメリットがあるか知りたい方は「借り換えサービス」をご利用ください。いずれも無料で、自宅にいながらオンラインでお申し込み頂けます。
まずは不動産投資ローンの事を知りたい方は『不動産投資ローンの教科書』を無料プレゼント中です!
【目次】
投資信託とは
投資信託の価格の基本である基準価格とは
投資信託を選ぶポイント
投資信託はリスク許容度の確認が大切
投資信託の購入金額
分散投資でリスクヘッジが可能
投資信託にかかる3つの手数料とは
まとめ 最初は少額から!投資信託を始めてみよう
投資信託とは
投資信託とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用のプロが株式や債券、不動産、ヘッジファンドなどに投資・運用する金融商品のことを指します。
様々な投資商品に分けて投資を行い、運用で増加した金額に応じて、投資家に還元します。
初心者が投資を行う際に、最も困ることのひとつとして、購入すべき銘柄の選択があります。
例えば、利益が得られそうな株を購入するためには、専門的な知識だけでなく、多種多様な情報が必要になるでしょう。
初心者にとってはハードルが高くなりがちですが、投資信託であれば、運用をプロにすべて任せることができますし、原則は株式の投資信託であれば複数の株式に分散投資をすることができるのでリスクを抑えた運用も可能になります。
投資の格言に、卵は一つの籠に盛るな、というものがありますが投資信託を購入するということは自然と複数の投資先に分散して投資をしてくれるということです。
また、投資に関する知識がなくても、始めようと思えばすぐに始められる点が、投資信託の魅力といえるでしょう。
投資信託の価格の基本である基準価格とは
投資信託を始めるにあたって、まず理解しておきたいのは基準価格です。
基準価格とは投資信託の今現在の価格のことで、株式でいうところの株価に近いです。
基準価格は証券会社のサイトなどで、確認できるようになっています。
値動きが時系列で示されたチャートを見ながら、基準価格の推移をチェックしましょう。
最近上がっているか、それとも下がっているか、そういった分析をしつつ、購入したい投資信託を決めます。
基準価格は日々変動するものの、変動するのは1日に1回のみです。
投資信託の数量
投資信託の数量は口(くち)と呼ばれる単位で数えられます。
株式で1株、2株と数えるのと同様に、投資信託では1,000口、1万口といった数え方をします。証券会社で投資信託を購入すると、基準価格に応じた口数が購入可能です。
基準価格は基本的に1万口あたりの価格となっており、投資信託の計算は1口辺りの価格ではなく、基準価格の1万口単位で考えたほうがわかりやすいです。
投資信託を購入し、その後基準価格が上昇すれば、1口辺りの単価も当然上がります。
結果、自分の資産も増えるということです。
投資信託を選ぶポイント
他の投資と同じように、投資信託も安い時期に購入、高い時期に売るというスタンスは変わりません。
このため、投資信託は長期的な目線でみて、基準価格が上がりそうなファンドを選ぶのがポイントです。
基準価格が上がると見込んでいても、下がるケースももちろんあります。
基準価格は投資信託に設定したコストを引いた内容で表示されています。
中長期で運用をすると考えたときに、運用コストが低い投資信託を選ぶほど、投資上のメリットは大きくなるでしょう。
後ほどコストに関しては詳しく解説していきます。
分配金の有無
投資信託を選ぶ際には、分配金の有無も大きなポイントになります。
分配金は、よく株の配当金と間違われがちでありますが、投資信託ごとに分配金を支払うかどうかを決めており注意が必要な点は必ずしもファンドの利益が出ているから出しているものでは無いということです。
株の配当金は、企業が利益を上げた中から支払われますが、投資信託の分配金は利益を上げていようがいまいが支払うと決めて運用しているのであれば支払われます。
例えば、毎月分配型であれば、毎月分配金が払い戻されますが、この分配金は発生するたびに、投資信託の基準価格を下げます。
もし分配金をもらっても使う予定はないまたは価格が上がることを目指しているのであれば毎月分配型であっても再投資型にすることで分配金を受け取らずに再投資して行くことができます。
投資信託はリスク許容度の確認が大切
投資信託を選ぶ際にはリスク許容度が重要になります。
投資の目的はお金を増やすことですが、人によって目指す方向性は異なるでしょう。
コツコツと値上がりすればそれでよい人もいれば、途中経過で多少値下がりしたとしても、最終的に大きく値上がりさせたい人もいます。
どちらかに偏らず、その中間辺りを目指す人も多いです。
価格変動に対して、どの程度我慢できるかのレベルがリスク許容度です。
投資信託を始める前に、投資額に対して自分がどこまでの損失を許容できるのか、具体的に計算してみましょう。
投資信託でよくある投資対象としては株式、債券、REIT(リート)などがあります。
外国の資産になると、為替変動がありますので、リスクはさらに高くなるでしょう。
逆にリスクが低い投資信託は国内債券です。
リスクを負って大きく資産を増やしたいのであれば株式やREITを、リスクを抑えコツコツやりたい人は債券を選ぶと良いでしょう。
バランスを重視する場合は、複数の資産を一定の比重でミックスした複合資産型が良いかもしれません。
投資信託の購入金額
投資信託はリスクの高いものから、低いものまで、いろいろな種類が揃っています。大きく儲けたいあまりリスクを冒しがちですが、リスクの許容度はしっかりと意識しておきましょう。
特に初心者のうちは、リスクの高い投資対象は額を小さめに、リスクの低い投資対象は額を大きめに配分したほうが安定します。
投資信託は1万円から投資できるようなものもあるので、試しにやってみたい人はそういったものを選ぶのもよいでしょう。
投資信託を積み立てて購入する場合は、1000円から投資できるケースもあります。投資信託は少額でも開始できるため、少しずつ慣れていくのがおすすめです。
分散投資でリスクヘッジが可能
投資信託を選ぶ際には分散されている資産の内容をチェックしましょう。
例えば、日本の株式や債券の資産だけでなく、外国の資産にも投資を分散させておけば、日本の株式の価格が下落しても他でカバーできる可能性が高くなります。
日本の景気が悪くても米国は好調というシーンはよくありますし、例えば通貨は日本円が安くなれば、ドルは高くなる関係です。
複数の通貨に資産を分散させるのは、リスク軽減のセオリーといえるでしょう。
一度に購入しすぎないドルコスト平均法
分散投資の概念は時間にも適用されます。
買うタイミングを複数回に分ける考え方で、ドルコスト平均法とも言われています。
例えば、毎月一定額ずつ購入していれば、安いときはたくさん購入できますし、高いときにはあまり買わずにすみます。
つまり、平均購入単価が抑えられるというわけです。
最安値のときに一気に買いたい人もいるかもしれませんが、そのタイミングを見極めるのは簡単ではありません。
複数回に分けてバランスよく購入するほうがリスクは軽減されます。
投資信託にかかる3つの手数料とは
投資信託の購入から保有、売却にかけて大きく3種類の手数料がかかります。
- 購入手数料
- 信託報酬
- 信託財産留保額
投資信託の手数料は投資の運用成績に大きく関わります。
投資信託説明書や、証券会社などで必ず確認をするようにしましょう。
それぞれ具体的に見ていきます。
購入手数料
購入手数料は、投資信託の購入時にかかる支払い手数料で、無料の場合もありますが、高いところだと3%ほどになります。
大手証券よりもネット証券のほうが比較的低くなっています。
また、同じ投資信託でも販売会社によって料金が違う場合もありますのでご注意下さい。
100万円で3%(税別)の購入手数料のファンドを買った場合には、評価金額は手数料を引いて約97万円になります。
購入すると同時に手数料が引かれて投資をすることになります。
信託報酬
信託報酬は投資信託を保持している間、日々支払われる費用で、費用の額はファンドによってまちまちですが、年率約0.05~3%が相場です。
株価指数と連動するインデックスファンドは信託報酬が低く目となっており、一方、利益を追求するアクティブファンドは手数料が高い傾向です。
保有している間、日々差し引かれるものになるのでなるべく低いものを狙うほうが運用効率面でも良いでしょう。
信託財産留保額
信託財産留保額とは、投資信託ならではの費用で株や債券をまとめて運用しており、これらのリバランス(資産の組み換え)には費用が発生しており、この費用のことです。
具体的な費用額はファンドによって異なりますが、0~0.5%ぐらいかかると見込んでおきましょう。
まとめ 最初は少額から!投資信託を始めてみよう

今回は、初心者が投資信託を購入する際に気をつけるべきポイントは?投資信託の選び方、注意点に関して解説しました。
投資信託は初心者でも始めやすい投資ですが、リスクはゼロではありません。
基準価格の動向に気を配ったり、自分のリスク許容度を把握したりといったことは必要です。
手数料に関しても、将来のリターンに大きく関連していますので、できるだけ低く抑えるようにしましょう。初めての方はいきなり大きな金額で投資をするのではなく、1万円程度の無理のない金額から始めてみて、毎月投資信託を積み立てるようにしてみましょう。
最後に、インベースでは、ご自身がいくらまで借り入れできるかを判定するバウチャーサービスを提供しています。
「不動産投資を検討しているが、いくら融資を受けられる?」
「どの不動産会社に相談すればいい?」
こうしたお悩みのある方はこちらからご利用下さい。無料でご利用頂けます。
借り換えを検討されている方はこちらから。国内最低水準1.575%のローンで借り換えできるか、借り換えするメリットがあるかどうかを無料で診断いたします。
【関連記事】