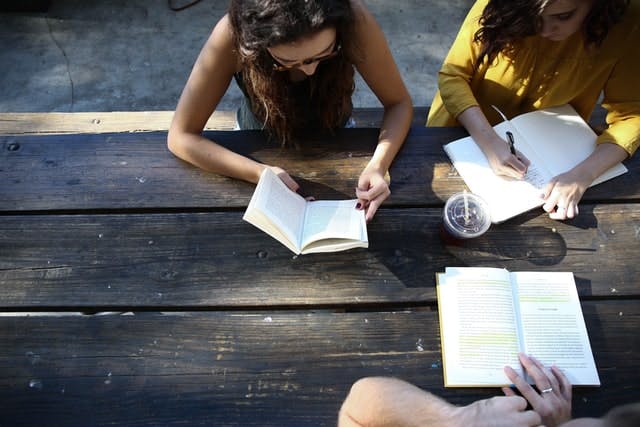老後資金2,000万円問題は、年金収入だけでは生活費が毎月赤字になることが根拠です。老後資金について具体的に考える際には、収入と支出のバランスを見直しましょう。老後資金の効果的な作り方として、資産運用についても紹介します。
※時間がない方へ・・・今すぐ不動産投資ローンの借り入れ可能額を知りたい方は「バウチャーサービス」、不動産投資ローンの借り換えができるのか、いくら借り換えメリットがあるか知りたい方は「借り換えサービス」をご利用ください。いずれも無料で、自宅にいながらオンラインでお申し込み頂けます。また、すでに購入したい物件がお決まりで不動産投資ローンをお探しでしたら「借り入れサービス」をご利用ください。
老後資金の2,000万円問題とは?
老後資金2,000万円問題は、2019年に提出された報告書をきっかけに話題になりました。老後の暮らしを支える資金として、多くの人が頼りにしている公的年金だけでは、生活費が足りないと公的に発表されたことを意味します。
2,000万円が不足するという計算の根拠を見ていきましょう。
老後の生活費が足りなくなるという問題
定年退職後は年金で生活しようと考えている人は多いでしょう。しかし2019年6月に金融庁の『金融審議会 市場ワーキング・グループ』がまとめた報告書によると、年金だけでは生活費が2,000万円不足するとされ、話題になりました。
夫婦2人の老後の平均的な生活費は、年金だけではまかないきれません。赤字を補填するためには、65歳を起点としあと30年ほど生きると考えると約2,000万円かかる計算です。
2,000万円不足するとされる根拠
夫婦2人暮らしで2,000万円の不足とされる根拠は、年金収入と平均的な支出の差にあります。定年退職後の夫婦が受け取れる平均的な年金受給額は月に約21万円です。
一方、2017年の平均的な高齢夫婦無職世帯の支出は月に『26万3,717円』で、年金受給額との差は『5万4,519円』と求められます。毎月約5万円が不足するという前提で、年金受給開始後の期間で不足分を求めると下記の通りです。
85歳まで生存(20年間):5万円×12カ月×20年=約1,200万円
95歳まで生存(30年間):5万円×12カ月×30年=約1,800万円
老後資金2,000万円問題は、この試算がもとになっています。
参考:金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」P.10,16,21|金融庁
参考:II 世帯属性別の家計収支(二人以上の世帯)P.28|総務省
老後資金への不安が広がる理由

老後資金への不安が広がっているのは、老後資金2,000万円問題によるものだけではありません。
平均寿命が大幅に伸びたことで、長寿がリスクと捉えられるようになったことも理由の一つです。加えて実質的に使えるお金が減っていることも、老後資金の不安につながっています。
老後の長期化という長寿リスク
日本人の寿命はどんどん伸びています。男性の平均寿命は80歳を超えており、女性も90歳に届く勢いです。平均寿命は今後も伸びていく見込みで、『人生100年時代』も現実的なものになってきているようです。
加えて2人に1人は平均寿命以上に生きています。そのため老後の暮らしを平均寿命までの期間と考えていると、十分な備えはできません。
『長寿リスク』と呼ばれるように、長生きするほど経済状態が悪化してしまいやすくなります。うれしいはずの長生きを不安に感じる人も出てきてしまうでしょう。
可処分所得の減少
寿命は伸びているにもかかわらず、高齢世帯の可処分所得は減少傾向が続いています。非正社員で働く勤労者の増加や、社会保険給付の減少の影響でしょう。
さらに自分たちで老後資金を用意するのも難しいのが現状です。労働者の月収はこの30年間で減少し続けています。しかし社会保険料や税金の負担は増加しており、可処分所得は減っています。
加えて物価は上昇しているため、実質的なお金の価値は目減りしている状態です。日々の生活で精一杯という家庭も多く、老後資金を蓄える余裕がないケースも多いでしょう。
『2,000万円も用意できない』と不安を感じている人も少なくありません。
必要な老後資金を計算しよう

老後資金の不安を解消するには、必要な老後資金の計算が役立ちます。定年退職後の収入はいくら受け取れるのか、生活費には実際にいくらかかるのかをはっきりさせましょう。
暮らし方によっては黒字になるかもしれませんし、老後の赤字額が2,000万円より大きいケースもあるかもしれません。
退職金や年金受給額の確認
まずは老後の収入がいくらぐらいになるかを確認しましょう。まとまった資金を受け取れる『退職金』は老後資金として、生活費に活用できます。
支給額は企業によって異なりますが、中小企業で1,400万円、大手企業で2,300万円が目安といわれています。この金額は大卒の場合で、高卒や短大卒での入社の場合にはこの9割ほどの金額です。
あわせて『年金受給額』も確認します。加入期間や支払った保険料によって受け取れる金額が異なるため、詳細は『ねんきんネット』で試算し求めるとよいでしょう。
『ねんきんダイヤル』や『電子申請』で申し込んでも、年金加入記録を教えてもらえます。
生活費を算出
次に『生活費』にいくらかかるか考えます。『令和元年度 生活保障に関する調査《速報版》』によると、夫婦2人の最低日常生活費は月に『約22万1,000円』です。最低限の暮らしに必要な支出には下記が挙げられます。
住居費
食費
水道・光熱費
被服・家事用品費
保健・医療費
交通・通信費
税金
社会保険料
ただしこの金額では生活するだけで精一杯でしょう。ゆとりのある暮らしのためには、月にプラス14万円の『約36万円』かかります。旅行・レジャー・趣味などを充実させるために必要な生活費です。
これらを目安として、実際に自分たちの暮らしに必要な費用を計算しましょう。
参考:令和元年度 生活保障に関する調査《速報版》 P.39,40|公益財団法人 生命保険文化センター
赤字分を埋める蓄えが必要
1カ月の収入と生活費が分かれば、赤字がどれだけ出るかが分かります。この赤字分が老後の期間全体でいくらになるか計算すれば、蓄えるべき老後資金がはっきりします。
総務省『2019年 家計調査(家計収支編)』によると、高齢夫婦無職世帯の可処分所得は月額『20万6,678円』でした。
これに対し実際の消費支出は月に『23万9,947円』で、毎月3万3,269円の赤字と分かります。このケースで65歳から95歳まで暮らしたとすると『1,197万6,840円』の老後資金を準備しておかなければいけません。
自分たちの生活実態に合わせた収入・支出で計算すれば、現実的に必要な蓄えがいくらか求められるでしょう。
参考:家計調査報告 家計収支編 2019年(令和元年)平均結果の概要 P.18|総務省
老後資金を蓄える方法

まとまった金額を用意する老後資金作りには、どのような方法があるのでしょうか?貯蓄を増やすために節約する方法のほか、副業による収入アップや、資産運用について解説します。
生活を見直し貯蓄を増やす
すぐに実践しやすいのが『貯蓄』です。貯蓄を増やすほどの余裕はないと考えていても、生活を見直すことで節約できる可能性はあります。
1カ月の支出を見直したとき、使途不明金があるなら、何に使っているか特定しましょう。レシートを貼ったりアプリを活用したりしてお金の使い道を記録すれば、使途不明金を減らすのに役立つはずです。
支出を見直せば貯蓄に回せるお金を確保しやすくなるでしょう。また節約の習慣が身に付けば、老後の暮らしにかかる支出も抑えやすくなるはずです。
支出を減らせれば赤字分が減少するため、老後の暮らしに余裕を持たせやすくもなります。
副業で収入を増やす
『副業』で収入を増やし、老後資金作りをするのも一つの方法です。節約では思うように貯蓄額を増やせなかったとしても、収入そのものを増やせば、その分を丸ごと貯蓄に回せます。
体力的な負担が少ない副業であれば、定年退職後も続けやすい点も魅力です。早いうちから副業のスキルを磨いておけば、リタイア後も副業で収入を得られるでしょう。
赤字分を副業で補えれば、用意した老後資金が少なくても乗り切れるはずです。副業が軌道に乗り独立開業できれば、安定収入を得られる可能性もあります。
資産運用を行う
お金に働いてもらう『資産運用』も老後資金作りに役立ちます。貯蓄も運用の一つですが、それだけでは思うように資金を増やせないかもしれません。
株式や投資信託などへ投資をすれば、効果的に資産を増やせるでしょう。現役で働いているうちから始めれば、長い時間を活用して退職時までにまとまった金額を蓄えやすいはずです。
退職後も長い期間があるため、資産運用を継続しましょう。ただし現役時代と比べて資産全体に対する運用金額の割合を下げると安心です。
資産運用で老後資金を確保しよう

低金利が続く中、老後資金作りをするには、資産運用も活用しましょう。こつこつ貯金を続けるだけでは、思うように資金作りが進まない可能性があるからです。
貯金から資産運用へシフトすべき理由
かつては預貯金をしているだけでまとまった金利が付き、お金が増えていきました。しかし低金利が続いているため、預貯金だけではお金がなかなか増えません。
加えてインフレが続き物価が上がっている点も、資金作りに資産運用を取り入れるべき理由です。物価が上がるとお金の価値は相対的に下がります。
これまで100円で買えていたコーヒーが150円に値上がりすれば、1,000円で10本買えたのが6本しか買えなくなってしまいます。お金の価値が半分近く下がったのと同じ状況です。
企業でも『企業型確定拠出年金』を導入するケースが増えており、自分の老後資金を自分で運用する方向へ変化してきています。
早く始めるほど有利
資産運用で老後資金作りをするなら、できるだけ早く始めるほど有利です。『複利効果』で資産が増えやすくなります。複利とは、利子にもまた利子が付くことです。
1万円を年利5%で運用すると1万500円になります。再投資すると1万500円に5%の利子が付くため1万1,025円です。このようにどんどん増えていきます。
積立期間40年・年利3%なら、毎月の積立金額は2万2,000円で2,000万円の資産形成が可能です。一方、積立期間が20年間であれば、積立金額は月6万2,000円なければいけません。
また複利で資産を倍にするのに必要な期間を計算するには『72の法則』が役立ちます。『72÷金利=資産が2倍になる期間』です。金利3%であれば24年で2倍になると分かります。
節税効果を得られるものも
資産運用の方法には『節税効果』が期待できるものもあります。例えば『iDeCo』であれば、投資資金は全て所得控除の対象となるため、所得税や住民税が軽減されます。運用益は全額非課税で、受取時も一定額までは非課税です。
『NISA』や『つみたてNISA』も運用益が全額非課税になります。また『個人年金保険』へ加入すれば、個人年金保険料控除の対象です。
『不動産投資』も節税につながります。不動産取得税・修繕費・火災保険・地震保険・減価償却費などの申告により、節税できるでしょう。
うまく活用すれば税金の負担を減らしながら運用できます。
資産運用は不動産投資がおすすめ

株式投資・投資信託・外貨預金など、資産運用にはさまざまな種類があります。その中でもおすすめは『不動産投資』です。インフレにも強く安定収入を得やすいため、老後資金の形成に役立ちます。
不動産投資で得られる二つの利益
不動産投資で得られる利益は二つに分類できます。購入した不動産を売却し差額で利益を得る『キャピタルゲイン』と、家賃収入を得る『インカムゲイン』です。
キャピタルゲインとインカムゲインはバランスを考慮しましょう。どちらもプラスになっているときはもちろん、どちらか一方のプラスがもう一方のマイナスを上回る場合にも、投資は成功といえます。
例えばキャピタルゲインが1,000万円の損失であっても、所有している期間にインカムゲインで1,000万円以上得られれば、全体では利益が出ている状態です。
現物資産でインフレに強い
『インフレ』に強いのも不動産投資の特徴です。インフレの物価上昇に伴い、現金や預貯金の価値は目減りします。しかし不動産投資は物価上昇に伴い家賃が少しずつ上がるため、インカムゲインの増加が見込めるでしょう。
また現物資産である不動産は、インフレになっても資産価値が下がりにくいのも特徴です。経年劣化による価値の減少は起こりますが、インフレにより急落するような事態にはなりません。
不動産をローンで購入していれば、借入金が目減りする点もポイントです。インフレ時はお金の価値が減少するため、借入金の価値も減少します。
長期間にわたり安定収入を得られる
長い間『安定収入』を得やすいのも不動産投資のメリットです。空室リスクへの対策ができれば、家賃収入が急に途切れることはありません。
特に人気エリアに保有している物件であれば、入居率を高く維持しやすいことに加え、不動産としての価値も維持しやすいでしょう。
企業の業績や市場の動向に左右されやすい株式投資と比較しても、安定した収入を得やすい投資といえます。
資産運用で老後に備えよう

定年退職後には年金や退職金で生活費をまかなうことになるでしょう。しかし年金収入のみだと生活費は赤字になり、65~95歳までの30年間で2,000万円近い赤字補填の資金が必要といわれています。
生活費の赤字額は家庭ごとに異なります。まずは退職後の収入額と支出の見込みを計算し、赤字が出るのか確認しましょう。赤字額がはっきりしたら、どのような方法でその資金を用意するか考えます。
早めに貯金を始めるのはもちろん、副業や資産運用も行いましょう。資産運用の中でも不動産投資は、インフレに強く安定収入につながりやすい運用方法です。
暮らしに合わせた資金作りをするなら、資産運用がポイントといえます。
「不動産投資を検討しているが、いくら融資を受けられる?」
「どの不動産会社に相談すればいい?」
こうしたお悩みのある方はこちらからご利用下さい。無料でご利用頂けます。
借り換えを検討されている方はこちらから。国内最低水準1.575%のローンで借り換えできるか、借り換えするメリットがあるかどうかを無料で診断いたします。
【関連記事】
>>不動産投資ローンはどの銀行がオススメ?金利や審査基準を比較