会社が税額の計算をしてくれるサラリーマンは、節税をするにしても限界があるでしょう。ただし、副業や非課税枠でできる投資に取り組むことで、節税につなげられる可能性があります。節税の基礎を解説し、サラリーマンでも実践できる節税方法を紹介します。
※時間がない方へ・・・今すぐ不動産投資ローンの借り入れ可能額を知りたい方は「バウチャーサービス」、不動産投資ローンの借り換え【特別金利1.575%〜】ができるのか、いくら借り換えメリットがあるか知りたい方は「借り換えサービス」をご利用ください。いずれも無料で、自宅にいながらオンラインでお申し込み頂けます。
まずは不動産投資ローンの事を知りたい方は『不動産投資ローンの教科書』を無料プレゼント中です!
【目次】
節税の目的
節税の基本は2種類
副業や個人事業で経費にできる条件
サラリーマンができる節税方法
不動産投資は節税効果大
節税の落とし穴に注意
制度を活用し節税を実践しよう
節税の目的
節税とは何のためにするものなのでしょうか。節税の目的と、意味を混同しやすい脱税との違いを解説します。
手元に資金を残す
税金はあらゆるものにかかっており、納税すると手元の現金が減ります。節税すれば納税額が減るため、より多くの現金を手元に残すことが可能です。
個人であれ法人であれ、納税後に多くの現金が残るのに越したことはありません。特に事業を営んでいる場合は、より多くの資金を残すことが経営の健全化につながります。
節税の中には、納税のタイミングを翌期以降に延ばせる方法がある点もポイントです。納税額が減るわけではありませんが、手元に残った資金を事業のために活用できます。
事業を進める上で、少しでも多くの資金を残しておくことを常に意識しておかなければなりません。経営が黒字でも資金がショートすれば、たちまち破綻に追い込まれる恐れがあります。
脱税との違いは?
脱税とは、本来支払うべき税金を、何らかの理由で支払わないことです。意図的に税金を少なく申告する悪質なケースだけでなく、経理上のミスで税額が足りなかった場合も脱税にあたります。
一方、定められた範囲内で税額を減らすことが節税です。脱税が違法行為であるのに対し、節税は法律上何の問題もありません。
支払わなくてもよい分の税金を減らせる節税は、むしろ積極的に意識すべきことです。控除や非課税制度など、節税につながる仕組みを知り、資金を残すために活用しましょう。
節税の基本は2種類

節税につながる基本的な仕組みとしては、経費の計上と所得控除が挙げられます。それぞれについて詳しく解説します。
経費を計上
所得税や住民税は、課税所得から控除額を差し引き、税率を掛けて算出されます。課税所得の金額に大きく関わるのが経費です。
課税所得額は、収入から必要経費を差し引いて計算します。必要経費を多く計上できれば課税所得額が少なくなるため、所得税や住民税の節税につながるという仕組みです。
必要経費には、事務所経費・消耗品費・旅費交通費・交際費・減価償却費など、さまざまな費用が該当します。経費にできるものとできないものを振り分けながら、できるだけ多くの経費を計上することが、節税を目指す会計処理の基本です。
所得控除を受ける
節税できる基本的な仕組みには、所得控除もあります。所得控除とは、課税所得から一定額を差し引ける制度です。
医療費控除・配偶者控除・扶養控除・寄附金控除など、所得控除は全部で15種類あります。特に対象者の多い控除が、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除です。
所得控除以外に、税金から一定額を直接差し引ける税額控除もあります。税額控除は全部で20種類(所得税額から控除される特別控除の特例を除く)あり、一般的なものとしては住宅ローン控除が挙げられます。
各種控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告により申請しなければなりません。医療費控除や寄附金控除は、会社員でも確定申告をする必要があります。
参考:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
参考:No.1200 税額控除|国税庁
副業や個人事業で経費にできる条件
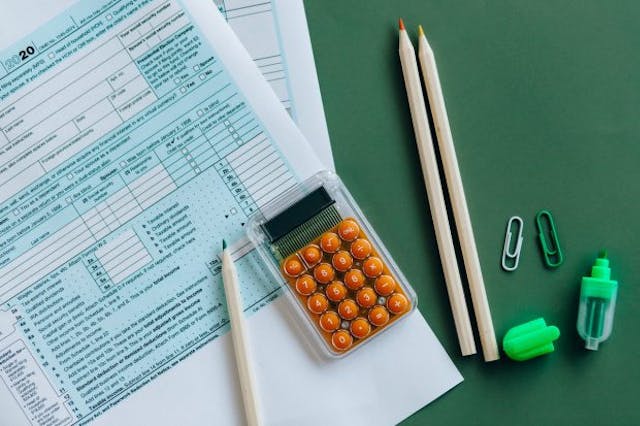
節税の基本である経費計上に関し、経費を差し引ける所得や経費に算入できる費用について、理解を深めておきましょう。赤字の所得を節税につなげられる損益通算についても解説します。
経費計上できる所得
所得の種類は、給与所得・不動産所得・事業所得・配当所得・退職所得・利子所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得の10種類に分けられています。
このうち、サラリーマンの副業や個人が営む事業で経費計上できる所得は、不動産所得・事業所得・雑所得の3種類です。その他の所得は、経費を差し引くことが認められていません。
サラリーマンが副業でパートやアルバイトをしている場合は、給与所得を得ることになります。経費は差し引けず、そのままの金額が所得として扱われます。
必要経費に算入できる費用
必要経費とは、事業を行うために使った費用です。分かりやすいものとしては、水道光熱費・通信費・旅費交通費・備品費・消耗品費・広告宣伝費が挙げられます。
税金に関しては、固定資産税や個人事業税を『租税公課』として経費計上することが可能です。不動産取得税・自動車税・消費税も、租税公課として扱えます。
事業資金として融資を受けている場合、利息分を必要経費に算入できます。ほかにも、各種保険料・従業員への給与・地代家賃・寄附金は、経費として扱える費用です。
参考:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|国税庁
必要経費に算入できない主な費用には、家族に支払う給与や所得税・住民税が該当します。罰金・過料・科料や家族のための地代家賃も、経費に算入できません。
損益通算できれば赤字でも節税効果がある
損益通算とは、赤字の所得を黒字の所得から差し引くことです。課税対象となる黒字分の所得額が減るため、損益通算できれば節税につながります。
損益通算の対象となる所得の種類は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の四つです。これらの所得で赤字が出た場合、給与所得などから赤字分を差し引けます。
黒字額よりも赤字額の方が大きく、損益通算してもマイナスになる場合は、翌年以降に赤字を繰り越して控除できます。繰越控除できる期限は3年間です。
サラリーマンができる節税方法

税金に関する手続きを会社が行ってくれるサラリーマンでも、自分で手続きすることで節税できる場合があります。主な節税方法をチェックしておきましょう。
ふるさと納税
サラリーマンが実践できる節税対策の一つに、ふるさと納税があります。ふるさと納税とは、好きな自治体を選んで寄附することで、所得控除を受けられる制度です。
控除上限額の範囲内であれば、寄附金額のうち自己負担分2,000円を除いた全額が、寄附金控除の対象となります。寄附した金額に応じて、自治体の特産品などを受け取れることから、近年人気を集めている制度です。
寄附金控除の申請方法には、確定申告とワンストップ特例制度の2種類があります。年間寄附先が5自治体以内のサラリーマンは、ワンストップ特例制度を利用できるため、確定申告を行う必要がありません。
NISAやiDeCoなど非課税の投資
資産運用を考えているなら、税制上の優遇措置を受けられるNISAやiDeCoの活用を検討しましょう。どちらも税制上のメリットを受けられます。
NISAは、株式や投資信託などの運用益が非課税になる制度です。一般NISAとつみたてNISAの2種類があり、運用益の非課税期間と年間の投資上限額が異なります。
自分で毎月掛け金を支払い、年金や一時金の形で老後に受け取る私的年金制度がiDeCoです。商品の運用益が非課税になる以外に、掛け金や受取金も税制優遇の対象となります。
資金を自由に引き出せるNISAは、住宅購入費や教育費の資金づくりに向いています。60歳まで資金を引き出せないiDeCoは、老後資金のための投資としておすすめです。
各種控除
住宅ローンを組んで自宅を購入・新築する場合は、住宅借入金等特別控除を活用できます。いわゆる『住宅ローン控除』と呼ばれるものであり、最大10年間の減税措置を受けられる制度です。
住宅ローンにおける年末残高の一定割合が税額控除できるため、大きな節税につながります。住宅ローン控除を利用する際には、サラリーマンでも初年度のみ確定申告を行わなければなりません。
自分や家族の入院・手術などにより、年間の医療費が高額になった場合は、医療費控除の制度を利用できます。支払った医療費に応じて所得控除を受けられる制度です。
医療費控除の特例として、特定の市販医薬品を年間で1万2,000円以上購入した際に所得控除を受けられる、『セルフメディケーション税制』も覚えておきましょう。
参考:No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
参考:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について|厚生労働省
不動産投資は節税効果大

サラリーマンが節税を意識しながら投資に取り組むなら、不動産投資がおすすめです。不動産投資の基礎知識や節税できる仕組み、サラリーマンに向く理由を解説します。
不動産投資とは
アパートやマンションなどの投資用物件を購入し、家賃収入や売却益で利益を得る投資方法が不動産投資です。一般的には、賃貸経営による安定収入を目指す方法が選ばれています。
不動産投資の主な種類は、ワンルーム投資と一棟買い投資の二つです。ワンルーム投資は分譲マンションの1室を、一棟買い投資は建物を丸ごと購入し、第三者に貸し出します。
一棟買い投資は、ワンルーム投資に比べ初期費用は高額になりますが、より多くの家賃収入を期待できます。一方ワンルーム投資は、異なる立地条件の複数物件に分散投資できる点がメリットです。
節税につながる理由
サラリーマンが行う不動産投資では、事業で赤字が出た場合、損益通算により節税できます。不動産所得の赤字分を給与所得から差し引くことで、所得税や住民税が減税される仕組みです。
経営不振による赤字だけでなく、物件の減価償却費を必要経費に算入し、帳簿上の赤字を出すことでも損益通算できます。減価償却費の金額が大きければ、キャッシュフローが出ていても所得を圧縮して節税につなげられるでしょう。
不動産投資での経営が軌道に乗り、大きな収益を上げられるようになってきたら、法人化することでも節税効果を得られます。所得が一定額を超えると、個人の所得税の税率に比べ、法人の税率の方が低くなるからです。
参考>>不動産投資は法人がオトク?途中から法人化する方法も解説
サラリーマンの資産運用に最適
不動産投資では、入居者募集や物件管理などの業務を、専門業者に一任できます。忙しいサラリーマンでも、時間や手間をかけずに取り組めるのがメリットです。
サラリーマンは収入が安定しているため、住宅ローンを組む際も審査に通りやすいでしょう。自己資金が足りない場合でも、物件を購入しやすくなります。
ローンを組む際に加入する団信が、生命保険代わりになる点もポイントです。返済中に契約者が死亡しても、団信から支払われる保険金がローン残債に充当されます。
これらの理由から、不動産投資はサラリーマンが取り組む資産運用の方法として最適です。将来の備えに不安があるなら、不動産投資を検討してみましょう。
節税の落とし穴に注意

少しでも税金を減らそうとして経費を増やすと、出費が増えて赤字経営になってしまう恐れがあります。節税を意識する際に注意すべきポイントを解説します。
経費を使い過ぎて赤字に
節税の基本は、より多くの経費を計上し、課税所得を減らすことです。しかし、経費を増やすことばかり考え過ぎると、無駄な出費が増えて赤字になりかねません。
決算前に消耗品などを大量購入し、不要なものが増えてしまうパターンは、典型的な浪費型の節税対策です。税金を減らせたとしても無駄な出費が増えれば、本末転倒と言わざるを得ないでしょう。
高額な固定資産を購入する際にも注意が必要です。取得価額が30万円以上の固定資産は減価償却の対象となるため、全額を一括で経費計上できません。
キャッシュフローが悪化
不動産投資で赤字が出た場合、給与所得と相殺することで節税できます。ただし、節税を意識し過ぎて無理に赤字を出そうとすると、キャッシュフローの悪化を招いてしまうでしょう。
不動産投資における最大の目的は、家賃収入で利益を獲得し続けることです。減価償却費など多額の経費を差し引いても、収支がプラスになるような経営を目指さなければなりません。
損益通算による節税効果は、あくまでも赤字が出た場合に限ったものであることを意識する必要があります。節税で得られるメリット以上の利益を目標にして取り組みましょう。
借入金の返済は経費にならない
投資用の不動産をローンで購入した場合、借入金の返済分は経費計上できません。借入金は売上として扱えないためです。
ただし、借入金を用いて購入したものに関しては、それらの購入費用を経費にできます。借入金で投資用物件を購入した場合は、取得価額を減価償却費として分割して経費計上することが可能です。
つまり、不動産投資においては、住宅ローンの借入金を減価償却費の形で経費にしていることになります。
借入金の元本以外に、自分の生命保険料や自宅の地震保険料なども経費にはできません。全ての支出が経費にできるわけではないことを押さえておきましょう。
制度を活用し節税を実践しよう

節税を意識すれば、より多くの資金を手元に残せる可能性が高まります。基本的な節税方法は、経費計上と所得控除の2種類です。
サラリーマンが少しでも税金を減らしたいと考えるなら、ふるさと納税や非課税投資、不動産投資などが適しています。さまざまな税制優遇制度を知り、節税のために有効活用しましょう。
最後に、インベースでは、ご自身がいくらまで借り入れできるかを判定するバウチャーサービスを提供しています。
「不動産投資を検討しているが、いくら融資を受けられる?」
「どの不動産会社に相談すればいい?」
こうしたお悩みのある方はこちらからご利用下さい。無料でご利用頂けます。
借り換えを検討されている方はこちらから。国内最低水準1.575%のローンで借り換えできるか、借り換えするメリットがあるかどうかを無料で診断いたします。
【関連記事】


















