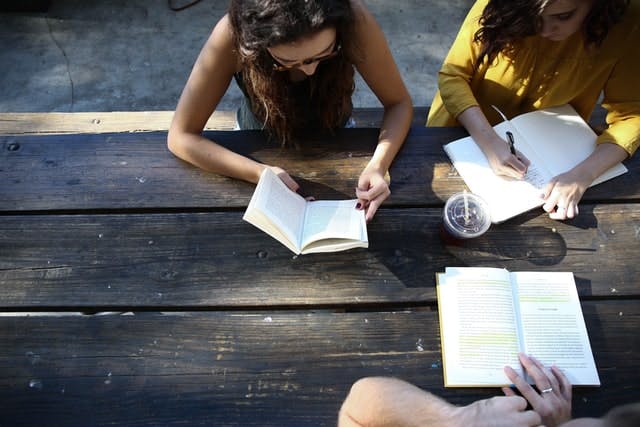預貯金や国債、貯蓄型保険はインフレに弱い資産です。物価が上がれば、これまでコツコツ貯めてきた『将来の備え』が大きく目減りしてしまいます。不動産や株式、外貨などに資産を分散し、インフレのリスクに備えましょう。
※時間がない方へ・・・今すぐ不動産投資ローンの借り入れ可能額を知りたい方は「バウチャーサービス」、不動産投資ローンの借り換えができるのか、いくら借り換えメリットがあるか知りたい方は「借り換えサービス」をご利用ください。いずれも無料で、自宅にいながらオンラインでお申し込み頂けます。
まずは不動産投資ローンの事を知りたい方は『不動産投資ローンの教科書』を無料プレゼント中です!
将来のインフレリスクとは
金融商品の実質的価値がインフレーション(インフレ)によって低減するリスクは、一般的に『インフレリスク』と呼ばれます。インフレが起こると、モノとお金の関係はどのように変化するのでしょうか?
インフレはモノの価値が上昇すること
『インフレ』はモノの価値が上昇し、お金の価値が下がることです。価値が下がれば、同じ通貨単位でも、購入できる商品や享受できるサービスが少なくなります。
マイナスのイメージを抱きがちですが、インフレがもたらすメリットも少なくありません。
例えば、日本円の価値が下がる『円安』の状況下では、日本の輸出産業が活性化し、企業の業績が上がります。海外からの観光客も増え、日本により多くのお金を落としてくれるようになるでしょう。
また、インフレでモノの販売価格が上がれば、小売企業の業績が上がり、社員の給与が上がることにも繋がります。給与が上がればよりお金を使うようになり、結果的に『好景気』へとつながるのです。
預金などの金融資産の価値は低下
モノの価値が上がり、これまで1,000円で買えていた品物が、2,000円出さないと買えない状況になれば、『お金の価値は2分の1に減った』といえます。
インフレでは、タンス預金や定期預金などで資産を保有している人は注意が必要です。金融機関に預金をすると『預金金利』が付きますが、物価上昇率に金利の上昇がついていけなければ、どうなるでしょうか?
これまでコツコツと貯めてきたお金の価値が大きく目減りし、生活が苦しくなったり、マネープランが狂ってしまったりする恐れがあるでしょう。
インフレ対策が必要な理由

インフレリスクに備え、多くの人は『インフレ対策』を始めています。今後は健康寿命がどんどん延び、年金だけではまかなえない老後になるとしきりに警鐘が鳴らされています。年金受給額が減少する可能性もあるため、さらなる備えが必要です。
長寿命化により必要な老後資金額が増加
日本人の寿命は年々長くなっています。厚生労働省の『令和元年簡易生命表の概況』によると、2019年の平均寿命は男性が81.41、女性が87.45で、前年度よりもそれぞれ0.1以上高い結果となりました。
寿命が長くなるのはよいことですが、考えなければならないのが『老後の資金問題』です。退職金や公的年金のみで老後生活がまかなえるとは限らないため、現役世代は今から『自己資金の確保』を始める必要があります。
定期預金や貯金で資金を確保している人の場合、インフレでは価値が目減りし、老後の生活が困窮するかもしれません。『インフレに強い資産』への切り替えを検討しましょう。
年金支給額が減る可能性
厚生労働省が発表する『平成30年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、厚生年金保険の平均年金月額は2018年度が約14万6,000円、国民年金の受給額は約5万6,000円です。
日本の年金制度は、現役世代の保険料で年金受給者の年金給付をまかなう『賦課(ふか)方式』です。少子高齢化で年金受給者が増えれば、年金受給額は今よりもグッと減ることが予想されます。
ゆとりのある老後生活に必要な金額は人それぞれですが、夫婦2人で月額30万円が必要な家庭を考えてみましょう。
夫が厚生年金、妻が国民年金の場合、年金自給額は月20万円程度にしかなりません。インフレで現金価値が目減りすれば、生活はギリギリです。
参考:平成30年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 P.27|厚生労働省
インフレに強い資産・弱い資産は?

『現金』はインフレに弱い資産の代表格です。ほかにはどんな資産がインフレで目減りしてしまうのでしょうか?資産価値を守るために今のうちから『インフレに強い資産』に切り替えていきましょう。
インフレに強い不動産や金など有形資産
インフレに強いといわれているのが『有形資産』です。『実物資産』とも呼ばれ、それ自体に価値がある資産を指します。
具体的には、金(ゴールド)やプラチナなどの『貴金属』や、建物や土地などの『不動産』、絵画や掛け軸、アンティークコインなどの『骨董品』などが挙げられます。
実物資産はインフレや金融危機に陥っても価格が急に下落しないのが特徴です。中には物価上昇と共に価値が上がる資産もあります。
デメリットを挙げるとすれば、管理に手間やコストがかかったり、盗難や紛失のリスクがあったりする点でしょう。
外貨預金、株も有効
インフレでは日本円の価値が下がり『円安』になります。預貯金が全て日本円の場合は価値が大きく目減りしますが、『外貨預金』を保有している場合は資産が増えるケースがあるのです。
ただし、外貨預金は為替相場の変動に影響を受けます。利益が出る場合もあれば、大きな損失が生じる場合もあるため、円建て資産と外貨資産をバランスよく保有するようにしましょう。
『株式投資』もインフレに強い資産といわれています。インフレで商品やサービスの価値が上がれば企業の儲けが増え、株価が上昇します。
安全資産ほどインフレに弱い
『安全資産』とは、相場変動などに影響を受けず、元本の減るリスクが少ない資産を指します。安全資産の代表格として、以下が挙げられます。
- 預貯金
- 国債
- 元本保証が付いた保険商品
- 年金
元本割れがない=安全というイメージを抱きがちですが、利回りが物価上昇率に追いつかなれば、損をしてしまうでしょう。
元本が保証されず収益性が変動する資産を『リスク資産』と呼びます。インフレ対策では、株・証券・不動産・債券などのリスク資産と安全資産をバランスよく持つことがポイントです。
不動産投資でインフレ対策は可能

『不動産投資』とは、自己資金やローンで不動産を購入し、賃貸経営や売却によって利益を上げる投資手法です。不動産投資には一定のリスクがありますが、会社員や個人が行うインフレ対策に適した方法の一つといわれています。
家賃収入は物価に伴って上昇
不動産投資では、マンションを購入して他人に貸し出す『賃貸経営』が主流です。インフレになると物価が上がって現金の価値が目減りしますが、賃料も上昇するため、不動産経営のオーナーは時代に合った収入が得られます。
昭和の時代は『インフレになると景気がよくなり社員の給料も上がる』といわれていました。
しかし、現代は『物価が着実に上がっているのに給料はそのまま』という状態が続いています。将来の資産を守るためにも、現金収入だけに頼らない方法を模索しましょう。
売却でキャピタルゲインを得られる
賃貸経営で家賃収入を得るほかに、売却により『キャピタルゲイン(売却益)』が得られるのも不動産投資の大きなメリットです。
インフレのときは、不動産の価値が上がります。物価が上昇したタイミングでうまく売却できれば『売却差益』が得られるでしょう。
不動産は一度手放したら収入が得られなくなってしまうため、最初は賃貸経営で長期的な安定収入を稼ぎ、まとまった資金が必要になった際に売却するという方法がおすすめです。
参考>>投資用マンションを高く売却するには?失敗をへらす5つの方法
借入により資産を持てる
不動産投資をする際、多くの人は金融機関から借入を行います。自己資金と借入金を併用することで、より大きな投資効果が見込めるためです。これらは一般的に『レバレッジ効果』と呼ばれます。
インフレ対策の一つとして『長期的な不動産投資ローン』を組む方法があります。現金の価値が目減りするインフレ下では、実質的なローン負担も軽くなるためです。
ローンの金利は『固定金利』と『変動金利』があります。固定金利の場合、返済中にインフレが起こっても金利は変わりません。
一方で、変動金利の場合は利率の見直しで金利自体が上昇し、月々の返済額における『利息の割合』が大きくなってしまうケースがあります。既にローンを組んでいる人は、インフレに備えて金利の見直しが必要でしょう。
ただし、不動産投資ローンの借り換えは自身で行うことは容易ではないため住宅ローンとの違いを抑えて行動する必要があります。具体的に下記記事にまとめていますので気になる方は御覧ください。
参考>>不動産投資ローンと住宅ローンの違いは何?上手に不動産投資ローンを借り換えする方法もご紹介
現物資産の不動産投資はインフレ対策に最適

日本人の多くは、定期預金や貯蓄型保険などで資産を管理する傾向があります。株や不動産、債券などのリスク資産は損失を被る可能性があるため、手を出さない方がよいと感じている人も少なくありません。
物価が上昇するインフレにおいては、現金は目減りします。老後のためにコツコツと蓄えてきた預貯金の価値が大きく下がってしまえば、暮らしは厳しいものとなるでしょう。
不動産投資はインフレに強い実物資産です。インカムゲインとキャピタルゲインの両方の恩恵が受けられるため、将来の大きな備えになるでしょう。
最後に、インベースでは、ご自身がいくらまで借り入れできるかを判定するバウチャーサービスを提供しています。
「不動産投資を検討しているが、いくら融資を受けられる?」
「どの不動産会社に相談すればいい?」
こうしたお悩みのある方はこちらからご利用下さい。無料でご利用頂けます。
借り換えを検討されている方はこちらから。国内最低水準1.575%のローンで借り換えできるか、借り換えするメリットがあるかどうかを無料で診断いたします。
【関連記事】